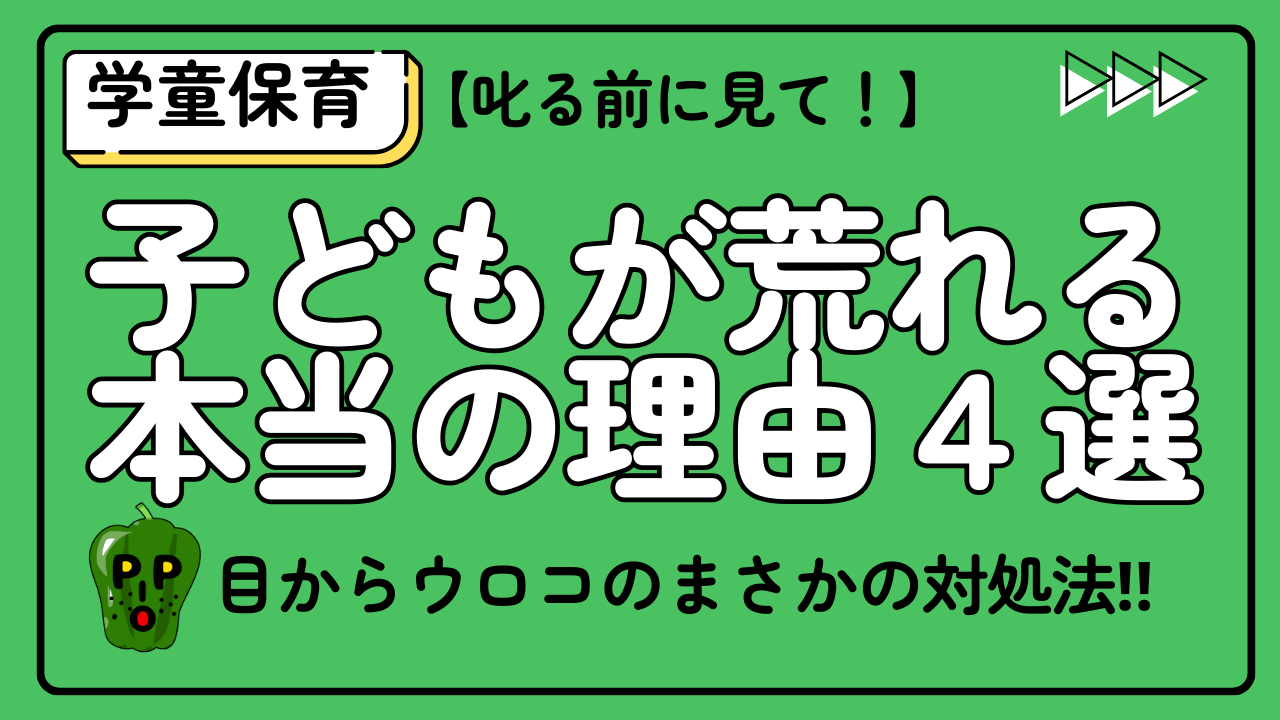おっかえりーっ‼学童系YouTuberのイオピーマンです!
「うちの学童、どうしてこんなに子どもが荒れてるんだろう…」 「もう指導員も疲れ果ててて、どうしたらいいか分からない!」
そんな風に感じている学童の先生、保護者の方、いませんか? 子どもたちが言うことを聞いてくれない、毎日が荒れまくっている…そんな状況、本当に辛いですよね。
でもね、ちょっと待ってください! 子どもたちが荒れているとき、そこには必ず理由が隠されているんです。
「そんなの理由じゃない!」って思うかもしれません。でも、理由を決めるのは私たち大人じゃない。子どもたちなんです。
今回の記事では、子どもが荒れてしまう「本当の理由」を4つご紹介!それぞれの理由に合った対応策も合わせてお伝えします。
このブログを読めば、子どもたちが単に「悪いことをしてやろう」「困らせてやろう」と思って行動しているわけではないことがきっと分かるはず。
さあ、一緒に「荒れない学童」を目指しましょう!
理由その1:「私を見てほしい」というSOS

「ねぇねぇ、見て!」「僕のことを見てほしい!」
実はこれが、子どもが荒れる一番多い理由だと私は思っています。
「ただのかまってちゃんじゃないの?」って思うかもしれませんが、子どもにとっては真剣な理由なんです。
- 自分を見てほしいから、友達にちょっかいを出す。
- 自分を見てほしいから、指導員に反発する。
「先生なんか嫌い!」って言う子に限って、指導員の周りをウロウロしたり、ちょっかいを出したりしませんか?
そうやって、必死に気を引きたいんですよ。
だから、私たちが「コラ!」って怒ると、子どもは「待ってましたー!」とばかりに喜びます。
机の上で飛び跳ねて「コラ!」と怒られると、「気持ちいい♪」と感じてしまう。
友達に暴言を吐いて「ダメだろ」と注意されると、「僕に注目してくれた!」と思ってしまう。
これが、子どもが荒れる本当の理由の一つ。
「寂しい」んですよ。
頑張っても誰にも見てもらえない、褒めてもらえない。だから、怒られる行動をしてでも注目されたい。
この負のループ、断ち切りたいですよね。
✨ 対応策:とにかく「抱きしめて」あげよう!✨
子どもたちの些細な頑張りに気づいて、「すごいね!」「よくやってるね!」と声をかけてあげましょう。
- 宿題を普通にやっている
- おやつを順番通りに取りに来ている
- いつもより静かに過ごせている
これらは当たり前のように見えるかもしれませんが、子どもにとっては「見てほしい」行動なんです。
他の指導員とも協力して、その子の「当たり前」を褒めていきましょう。
悪口大会や愚痴大会にならないように、ポジティブな視点でその子を見てあげてくださいね。
「悪いことをしなくても、先生たちはちゃんとあなたのことを見ているよ!」というメッセージを伝えることが、子どもの安心の土台を築く第一歩です。
理由その2:ストレス発散「大爆発バーン!」

学校や家でのストレスが「大爆発ボン!」これが2つ目の理由です。
「学童保育はストレス発散の場所なの?」と思うかもしれませんが、そうなんです。
学童保育は、子どもたちが放課後に解放される場所。自分の思いをありのままに出せる時間なんです。
我慢することなく、思いを全て出せる場所であることを保証してあげるのも、学童保育の役割の一つです。
学校で一日中「いい子」でいたり、家で保護者の方に認められたくて「いい子」でいることに疲れてしまう子どもたち。 本当は遊びたい、ケンカもしたい。
でも、「あれダメ、これダメ」「ちゃんとしなきゃダメ」と言われ続けて、たくさんのストレスを抱えています。
そのストレスが限界に達すると、学童で大爆発してしまうんです。
✨ 対応策:とにかく「抱きしめて」あげよう!✨
ストレスMAXの子どもたちには、共感が何よりも大切です。
例えば、学校で係決めがうまくいかなかった子が、学童で宿題のプリントをぐちゃぐちゃに丸めてしまったとします。 ここで「宿題を丸めちゃダメ!」と正論を言っても、子どもは余計ストレスを抱えてしまいます。
まずは「どうしたの?」「何があったんだ?」と子どもの話を聞いてあげましょう。
そして、「なるほど、そんなことがあったんだね…」と、その子がそうせざるを得なかった気持ちに共感してあげること。
私たちは、子どもたちの気持ちを受け止めるクッション役です。
そうすることで、暴れ回っていた子が落ち着いたり、先生になら話せると思って心の内を打ち明けてくれるかもしれません。
子どもにとって学童が安心できる場所になるよう、ストレスを抱える子どもの気持ちを理解してあげましょう。
理由その3:できない自分を責められたくない!
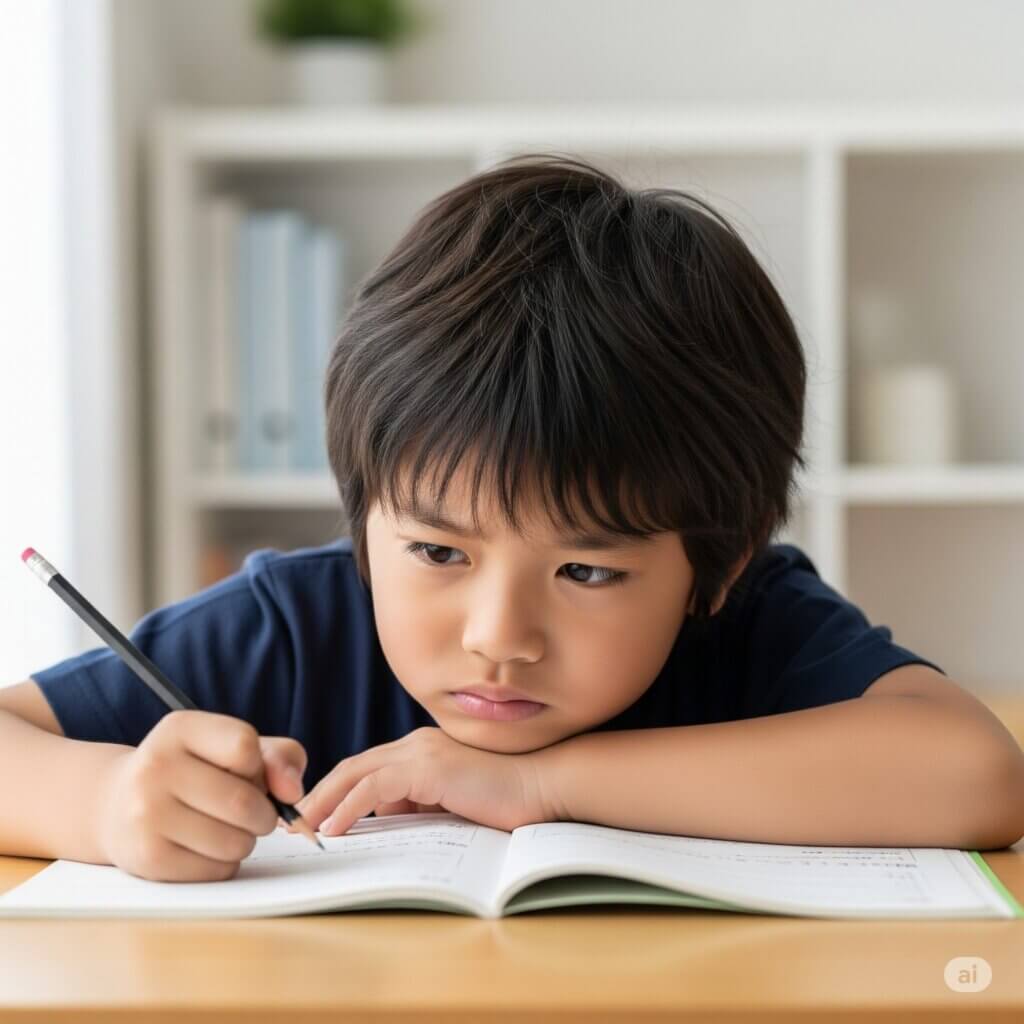
子どもたちは「やらない」のではなく、本当は「できない」ことがあります。
できないから、むしゃくしゃする。
できない自分を認めたくないから、強がったり、誰かに攻撃的になったりするんです。
- 宿題が苦手だから、宿題の時間に荒れる。
- 嫌いなおやつがあるから、おやつの時間に走り回る。
- 自分に自信が持てなくて、年下の子に強く当たってしまう。
周りから見たら「そんなにできないことないじゃん!」と思うことでも、その子にとっては「できない」というコンプレックスを抱えている場合があるんです。
完璧主義タイプの子どもにも当てはまることがあります。
失敗したくないから、新しいことにチャレンジできない。 ドッヂボールで本気を出して当てられたらプライドが傷つくから、わざと失敗して「ほら、できないだろ?」と自分を守ろうとする。
誰かに責められたくない、という強い思いがあるからなんです。
✨ 対応策:とにかく「抱きしめて」あげよう!✨
「大丈夫だよ」「失敗してもいいよ」という安心感を与えることが、私たち指導員にできることです。
「あなたはそれができないと思っているんだね…」と、まずは子どもの気持ちに共感してあげましょう。
「イオピーマンはそうは思わないけど、あなたはできないと思っているんだね。だから辛いね…」と、その気持ちを理解してあげるんです。
小さな安心感を与える声かけの積み重ねが、子どもにとって学童保育を安心できる場所へと変えていきます。
できないと思っている子、わざと失敗する子、そしてそれによって荒れている子がいたら、その「できない」という気持ちを理解して、「辛いね」と共感してあげてください。
理由その4:比較されて傷つく「グサッ!」

「○○ちゃんはできていたよ」「○○くんを見習って」
私たち指導員は励ますつもりで言ったとしても、子どもたちは「あの子に比べたら、俺はダメなやつなんだ…」と深く傷ついてしまうことがあります。
これが4つ目の理由です。
「他の子に迷惑をかけているぞ」「みんなやってないのに、お前だけやってるだろう」 私たちは比較しているつもりがなくても、子どもにはそう伝わってしまうケースは少なくありません。
特に、比べられることに過剰に反抗したり、ナーバスになったりする子どももいるんです。
比較されることで傷つき、それが原因で荒れてしまう子どもに、私たちはどう関わればいいのでしょうか?
✨ 対応策:とにかく「抱きしめて」あげよう!✨
「あなたはあなたのままでいい」「そのままのあなたで大丈夫。ありのままで愛されているよ」
こんなメッセージを伝えることが、何よりも大切です。
「でも、暴れている子をそのまま受け入れたら怪我するんじゃないの?」
「わがままを許すことにつながるんじゃないの?」
そう思われる方もいるかもしれません。
でも、これはわがままを許すことや、危険な行動を全肯定することとは違います。
丸ごと受け入れるのは、子どもの「気持ち」の部分なんです。
例えば、階段の手すりに登って遊んでいる子がいるとします。
危険な行動なので、「危ないから降りなさい」と注意することは当然必要です。
しかし、その子がなぜ手すりで暴れてしまうのか、その裏にある気持ちに寄り添うことが大切なんです。
もし、他の子と比べられて劣等感を抱えているのだとしたら、そのモヤモヤした気持ちを指導員がちゃんと聞いてあげて、理解しようと働きかける。
私たちが注目するのは、その子の気持ちや心の動き。
危険な行動は止めつつも、その子がなぜそうせざるを得なかったのか、その気持ちを認め、受け入れてあげましょう。
「抱きしめる」ことが、すべてを解決する鍵!

今回、子どもが荒れる理由を4つご紹介しましたが、対応策はすべて「抱きしめる」という一つの答えにたどり着きました。
私たち学童保育の指導員に求められるのは、子どもたちの気持ちを丸ごと受け入れ、共感し、その心を抱きしめてあげることなんです。
ただ「コラ、やめなさい!」と脅して行動を止めさせるだけでは、本当の理由は何一つ解決しません。
叱る前に、子どもがなぜそうせざるを得なかったのか、その理由に目を向ける。
これは、普段から子どものことをよく知り、一緒に生活している私たち指導員だからこそ気づける視点です。
「安全管理のおじさん」ではできない、私たち指導員だからこそできる「生活づくり」の視点を大切にしていきたいですね。
これからも、学童保育の情報をポップでライトに、皆さんにお届けしていきます!
学童系YouTuberのイオピーマンでした! じゃあねー、バイバイ!
もっと子どもの気持ちを理解しようぜー!

🌟 イオピーマンとつながろう! 🌟
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。
 youtubeもよろしくね♪
youtubeもよろしくね♪じゃーねー





最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ご意見、質問感想、何でもお待ちしていまーす‼


- イオピーマンのYouTubeチャンネル登録はこちら!
- ブログの感想や質問、あなたの学童でのエピソードもコメントで教えてね!