
子どもを叱る上でポイントってあるの?
子どもに響く叱り方が知りたーい

いい極意が2つあるよー
今回は「学童保育で子どもを叱る極意」についてイオピーマンなりに簡単にわかりやすくお伝えしていきます。
この記事を見ることで「子どもを叱るポイントとその極意」について理解できるようになります。
そうなることで、子どもたちに伝えたいことが子どもに伝わり、学童保育の生活はみるみる安定してきます。
今回はとっておきの2つの極意をご紹介しますので、どうぞ最後までお付き合いください。
叱る極意⁉

子どもたちを叱るケースは様々あります。
そしてできることなら、叱ることなく子どもたちに伝えたいことが伝わることが望ましい…指導員なら誰しもがそう願っています。

しかし‼
- 一日に何度も…
- 一時間に何回も…
- 一分間で数回…
叱るケースが訪れることがあります。そして

私だって好きで怒っているわけじゃないわよ‼
いい加減にしなさーい‼
となってしまいます。
叱るのが嫌になります。
そして落ち込みます。
だけど安心してください。
今回は大体どんなケースにも大体うまくいく叱る極意を伝授します。

2つあるよ…
意識してみて、一度と言わず何度か…試してみる価値はあります。
叱る極意①叱ったあとが勝負

子どもを叱る極意は、叱ったあとに訪れます。

えーっ
叱ったあと⁉
叱り方については、ひとまずおいておきます。

どこにおくの?
指導員が子どもを叱ったあとの、その子の行動に注目してみます。
例えば…
机の上をピョンピョン飛び回る子どもを叱るとします。

何でそんなことするんだ‼
あぶないだろーっ
叱り方はさておき、そのあとそれでおわらないことがポイントとなります。
子どもを叱ったあと…子どもが一時的にでもピョンピョンするのをやめた場合に、すかさず声をかけます。

- 落ち着いて過ごしているね
- やればできると思っていたよ
などの声をかけます。
これは子どもたちが

- 気にかけてもらえている…
- 見てもらえている…
という気持ちになるきっかけとなります。
子どもは指導員に見てもらうことで、安心できます。
指導員は、叱ったあとも放ったらかしにしません。
これは監視や管理ではない関わり方です。それは

- あなたのことを
- よく見ているよ
- 気にかけているよ
なぜなら、あなたはこの学童保育で幸せに過ごせる大切な子どもだからね…
という「あたたかいまなざし」で見る関わり方です。
この関わりはずっと続きます。
次の日は

今日はぴょんぴょんしてないね
ちゃんとできているね
一週間後は

最近ぴょんぴょんの数が減ってきたね

ずっと見てる…
これは一ヶ月、一年、それ以上続ける関わり方です。

えーっ
そんなのは現実は無理…
その子だけをみているわけじゃないしねー
と思うのは理解できますし、事実そうです。
しかし、叱ったあともその子の行動に注目して、その後も声をかける関わり方を試すことはとても効果的です。
指導員は子どもを叱った責任があります。
叱っておわり…では、子どもたちも叱られておわりと感じ、またその叱られる行動を繰り返します。
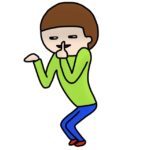
- 見られていない…
- バレない…
- おもしろくない…

またしてやろう
ぴょんぴょんしないのは当たり前…と感じますが、 「その当たり前…」ができた瞬間にすかさずその子に声をかける関わりがポイントとなります。

テクニックいるねー
子どもはみんな

見てもらいたい
関わってもらいたい
と思っています。
叱ったあとの関わり方が大切…これが1つ目の極意でした。
極意②俳優になれ‼

指導員が子どもを叱るときは、俳優になったつもりで演技します。

俳優⁉️おもしろそう
なぜなら、叱る演技をすることで、自分のことも周りのことも客観的に見ることができるからです。
叱るときの感情も、演技に含んでしまいます。

もういい加減にしなさい
ピョンピョンすることが迷惑になっているのがわからないの?!
と怒っているように見えても、実際は怒っていません。
それは叱る演技をしている状態です。

あっぱれ…
子どもを叱るケースは、子どもに何かを伝えるケースです。
その伝え方の1つが「叱る」ことです。
子どもを叱る演技をして、子どもたちに伝えたいことを伝えます。
なぜなら
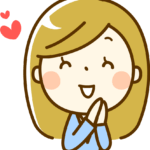
ピョンピョンするとあぶないピョン♥️
と笑顔で言っても伝わりにくいからです。
指導員は俳優になったつもりで、いろいろなシチュエーションで演技をします。
それは叱る演技に留まりません。

- ほめる
- 寄り添う
- 涙する
演技も、ときに必要となります。
また

指導員も人間だろ‼️
演技なんてしてないで心と心でぶつかり合うべし‼️
という理論も理解できます。
しかし、演技することは、子どもと向き合っていないことではありません。
子どもたちのことを思って、いい学童保育をつくるためになら、

演技でもする‼️
俳優にもなる‼️
という向き合う心がそこにあります。
冷静に客観視しながら、自分の関わりや演技を振り返り、次の言葉とセリフにつなげていきます。
そういう意味で指導員は、俳優でありながら、脚本家であり監督でもあります。

台本なし…
とっさに判断…
学童保育のドラマを輝かし、感動の渦に巻き込むような保育は毎日オンライン中です。

ライブ配信中
指導員俳優の注意ポイント
ここで俳優たる者の注意点をザーッとまとめてみます。
- 途中でやめない、キャラを変更しない
- セリフの棒読みにならない
- 感情が入り込みすぎて、一人で盛り上がってしまわない
- 真面目に捉えすぎない
- 子どもを脅さない
叱る演技をする上で「子どもを脅さない」ことは最重要ポイントとなります。
演技だからといって、恐怖、威圧で子どもたちをコントロールする関わりは許されません。
もしそれで事が済むなら、特別出演でゲストで鬼役を呼んでくることで解決してしまいます。

悪い子には誰じゃー
これはナイス保育ではありません。
演技と言えども、子どもを脅すようなことがないように注意を払います。

むしろ
それは保育じゃない
ただの脅し…
大切な視点は
- 子どもたちと冷静に向き合うことができるように
- 子どもたちに伝えたいことが伝わるように
です。
そのために私たちは演技をし、俳優になります。
- 情熱いっぱい
- 知的で落ち着いた
- 厳しくて優しい
- かっこいい
など、その時、そのタイミングでその子に応じた最適な役柄を演じきることで、その子に応じた最適な支援ができることにつながります。
心の中で

演技、役者、俳優
と意識することで、どんどんその力は培われてきます。
一度と試してみてはいかがでしょうか?
まとめ

子どもを叱る極意は2つあります。
1つ目は「叱ったあとが勝負」です。
子どもたちのその後の様子を観察し、
- 気にかけてあげる
- 声をかけてあげる
ような「あたたかいまなざし」をもち続ける関わりが大切です。
子どもたちはみんな

- みてほしい
- 関わってほしい
と思っています。
極意2つ目は「俳優になれ‼️」です。
指導員は叱るとき、俳優になって演じきります。
そうすることで、冷静に客観的に自分と周りを見ることにつながります。
叱る以外でも色々な役者になって、子どもたちの幸せや子どもの最善の利益に基づいた関わりを意識することが重要です。
子どもたち一人ひとりに合ったセリフを即座に考えて、伝えたいことが伝わるように演じきります。

- 指導員の仕事って楽しい
- 保育っておもしろい
と感じることで、叱る演技も上手くなってきます。
叱る極意は、子どもたちに伝える極意です。
最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。

じゃあねー
ユーチューブもみてね⬇️

