 新人
新人子どもとあそぶって何?
どうやってあそんでいいかわからない…



ポイントを5つお伝えするね
今回は新人指導員が子どもとあそぶポイントについて、イオピーマンなりに簡単に、わかりやすくお伝えしていきます。
この記事を読むことで、子どもとあそぶポイントが理解できるようになります。
そうなることで、子どもといい感じであそべるコツがつかめます。
そしてそれは子どもとの信頼関係づくりと結びつきます。



今すぐ子どもといっぱいあそびたーい
と思ってしまうほどナイスな内容となっていますのでどうぞ最後までお付き合いください。
①環境が大事


子どもがあそびを充実させるために「環境」はとても大切です。
なぜなら、何もないところからあそびを生み出すのはむずかしいからです。
例えば、どこかの会議室を借りてきて、子どもに「あそびなさい」と声をかけても、発想豊かにあそびを展開させることはできません。
あそびには「時間・空間・仲間」の3つの間(さんま)が必要と言われています。





空間=あそべる環境です。
遊具とかおもちゃとか…学童保育には必要です。



あそびの環境構成を整える
子どもが環境との交流を持ち始めるまでは積極的に、交流が始まったら消極的になりなさい。
マリア・モンテッソーリ
とあるように、指導員は子どもがあそびだすまでの準備や導入に力を入れて、あそび出したあとは子どもに任せることが大切です。
適切な環境さえあれば、子どもは自分たちであそびます。



あそぶ力を持っている
「子どもたちがいい感じであそびだしたら、指導員はそっと抜け出して様子を見守る」このバランスを大切にします。



ポイントはバランス…



あそびすぎず
見守りすぎず
子どもがあそぶきっかけをつくり、子どもの主体性を信じる…このあたりを意識して子どもとかかわることをおすすめします。
環境に心を配る
今使っている遊具やおもちゃが、使いやすい状態であるか…壊れたり片付けにくい状態になっていないか…をチェックすることが大切です。
なぜなら、遊具やおもちゃが大切に使われている学童保育は、子どもが安定して過ごせることに繋がっているからです。
あそびが充実していると、子どもは落ち着きます。
指導員として、子どもと一緒にあそびながら、あそびの環境が整っているかをチェックすることが求められます。



使いやすい?
片付けやすい?
ボロボロになってない?
例えば、トランプで言うと
- 枚数はそろっているかどうか…
- ジョーカーが折れたり傷がついたりしていないか…
などです。



ジョーカーがやぶれていると、ババ抜きをしているときに「あっ、あれ絶対ジョーカーじゃん」と相手にバレてしまうからおもしろくなくなる…
子どものあそぶ気力は、このように、環境によって左右されます。
指導員として、子どもが使う遊具に関心を寄せることが重要となります。
- このボードゲームはルールがわかりにくいな…説明書をカラーコピーしてラミネートしてみよう…
- 一輪者のサイズは16センチが人気だから、いつも誰が使うかでモメているな…一輪車の数を増やすか順番表を子どもと一緒につくるのはどうかな…
- 片付けの箱がボロボロになっているな…新しいのを購入して、パーツごとに収納するようにしたら次使う時に使いやすくなるかも…
というように指導員が一つひとつ丁寧にあそび道具について気をかけることがポイントです。



あそびの環境構成を整える
子どものあそびが充実したものになるかどうかは、指導員の準備力にかかってきます。
指導員のモノに対する意識が、あそびの充実と発展に大きな影響を与えます。
そのあたりが1つ目のポイントでした。
②あそび仲間


指導員は子どものあそび仲間になります。
子どもにかえったつもりであそびます。



つもり!!
子ども目線になることがポイントです。
子どもから見たらこの光景がどうみえるのか?自分が子どもだったらきっとこうするはず…と意識しながら子ども目線に近づきます。
大人目線にならないように注意が必要です。
例えば、子どもと一緒におままごとをしていて遊んでいるとします。



そうだっ
お店屋さんのレジはこの場所に移動させて、店員さんはこっちにいた方がよくて、こっちからお客さんにメニューをきいた方がいいよね、ほらこうしたほうが効率よく人を誘導できるでしょっ‼
など大人だから子ども以上に気づいてしまうこともあります。
しかし、子どもがやりたいようにお店のレイアウトを任せたり、一緒にその効率が悪いように思うあそびをして、あえてその部分を楽しむことも大切です。
この場合、子どもはレイアウトとか効率のいい流れなどに興味はありません。
子ども目線になって、子ども世界の一員になることを心がけてみます。
➡学童保育指導員が子どもたちとあそぶ価値は?あそぶことは仕事ですよ‼
しかし



子ども目線…と言われてもむずかしいわ
何十年、大人をしていると思っているの?
今更、子どもになんか戻れない…
という方もおられることでしょう。
そういう方に試してもらいたい方法があります。
その名もすべていいなり作戦です。
すべていいなり作戦
まずは子どものあそびに入れてもらいます。



何したらいいの?
と聞いてみます。
そして
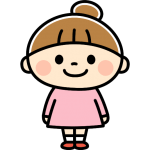
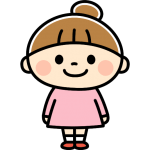
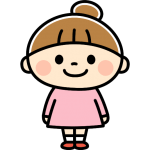
お客さん役をしてほしい
あとはお金をつくて…
と子どもに言われるがまま、あそんでみてください。
いいなり作戦は、作戦です。
子どもに聞いてみて、仲間に入れてもらい、少しずつ関係をつくっていく作戦としてあそび世界にもぐり込むことを試してみてください。



子どものあそび世界に潜入
子どもはきっと色々と指導員にお世話を焼いてくれます。
おおらかな気持ちで、一緒にあそぶことがポイントです。
変なプライドや大人としてのこだわりを捨てて、子どもに仲間に入れてもらう。
そこから、子ども世界に潜り込むことができます。



仲間に入れてもらう
③あそびをリード


子どもをグイグイ引っ張りあそびをリードします。
一緒に豪快に遊んだり指導員が見本を見せるパターンです。
ここでは「指導員自身の特技を活かす」というところに意識をおきます。
- 野球ができる人は、その力を存分に出して引っ張っていきます。
- 折り紙が上手な人は、美しい作品をつくって魅了します。
- 編み物が得意な人は、上手に編んで「すごい」と思わせます。
特技は、そのまま保育に生かすことができます。
子どもが



すごーい
やってみたい♬
という気持ちをかりたてるほどの技があればそれは指導員自身の武器となります。
技術ほどではなくても、ちょっと得意なこと、好きなことでも大丈夫です。
ぐいぐいとあそびを引っ張っていく気持ちだけでも、それはそれで立派な武器となります。
そこに子どもは魅了され憧れを抱きます。



あつまれー
一緒にあそぼうよ
子どもによっては、



「何をしてあそんだらいいかわからない…」
「ひまだけど、なかなかうまくあそべない…」
と思って学童保育で過ごしている場合もあります。
その子にとって、グイグイ引っ張ってあそんでくれる指導員がいたら、その子の心は軽くなります。



わーい
あそびたーい
指導員の「一緒にあそぼう」の一言が子どもを救うこともあります。
子どもは見本となる人のマネをしたり、憧れを抱くロールモデルがあることで、あそびの力をぐんぐん伸ばすことができます。



指導員は憧れの的♪
時には、豪快にあそびをリードすることで、このような子どものあそぶ力を引き出すことに結びつきます。
自分自身が少し得意なことや好きなあそびでも保育に活かせることができるのがポイントです。



強引に引っ張ってほしい
④見守るかかわり


子どもがあそんでいる様子をよくみて、よく洞察することは指導員として重要です。
ときに指導員は子どもを見守ることを大切にします。



ただ見ているだけではなく、子どもの行動や心の動きまでよく観察…
子どもは、大人が介入しなくても、自分たちであそびはじめ、あそびを発展させることもできます。
子どもが環境との交流を持ち始めるまでは積極的に、交流が始まったら消極的になりなさい。
マリア・モンテッソーリ



モンテっソーリ
子どもの可能性を信じて見守ることはとても大切です。
これは、無視とか放任することは意味が違います。



ほったらかし…とは違う❌
「見守る」は、見て守るのです。
ただ見ているだけでもありません。
意図的に見守る
指導員は意図的に子どもを見守ることが求められます。
ただ「ぼーっ」と見ているようでは、それは保育とは言えません。



この子にとっての…
課題や「つまづき」は?
指導員に意図があれば、それは保育となります。
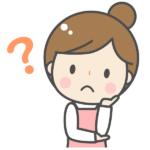
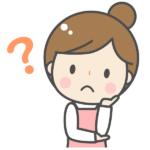
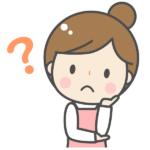
最近はナスビくんとキュウリくんが一緒にあそぶことが少ないなー
何かあったのかもしれないなー
しばらく様子をみて、あとでさり気なく声をかけてきいてみよう



なかなかドッチボールがはじまらないなー
いつもまとめ役のタマネギ君が今日はいないからかー
だれが声をかけて、ドッチが始まるかを見守ろう
など、子どものことをよく観察し、よく考察し、次のはたらきかけにつなげるために、あえて見守る働きかけをすることはとても重要です。



そういうのが
意図だね
ただ安全だけに目を向けるのではなく、子どもの行動や心の動きに目を向けて、観察と洞察をすることが指導員の見守りというかかわりです。
見守るポイント
見守るかかわりは、その距離感が重要です。



遠くでぼんやり見ているだけ…
近くで目を見開いてギョロっと見つめる…
これでは「見守るかかわり」とは言えません。
イメージすると、
何か子どもに問題が生じた時に、子どもにとって絶妙なタイミングで指導員が現れたように振る舞いますが、実は近くで指導員がさりげなく見守っていた…



こんな感じ↺
見守るとは、そういうことです。
子どものあそびの邪魔をしないようにしながら、必要な時に適切に対応できるようにしておくことが大切です。
このように指導員は「意図と願い」をもちながら、観察と洞察をします。
そこがポイントです。
「見守るかかわり」は、決して楽なものではなく、むしろ高度な技術を要します。
できることから、意識して「見守るかかわり」を習得していきましょう。
⑤あそびの「指導」


子どものやりたい気持ちを引きだす働きかけのことを指導と呼んでいます。
「指導」とは何かを厳しく注意したり、やらせたりすることではありません。
➡︎学童保育指導員と支援員の違いは?「指導」本来の意味を解説‼
これは、これまでのポイント①〜④のすべてに共通する考えです。
子どものやりたいとか、あそびたいという気持ちを上手く引き出すことが指導員に求められます。



主体性や自主性を引きだす
①環境を整える…
②仲間となる…
③ロールモデルとなる…
④見守るかかわり…
という指導(働きかけや導き)を指導員は行います。
あそびを指導とは、子どものやる気を引きだすことです。
それは子どもの



おもしろそう
やってみたい
が湧き上がるような仕掛けを用意することです。
私たち指導員は「あの手この手その手、奥の手」を使いながら子どもの



おもしろそう
やってみたい
を引き出します。
自ら楽しむ、ワクワク
まず、はじめに意識したいことは、指導員自身が「楽しむ、ワクワクする」ことです。
自分が「おもしろいと思うこと」を軸に子どもをやる気の世界に導きます。
- コマ回しをやってみたい
- 工作とか充実させたい
- 紙飛行機づくりを極めたい
- ボードゲームで盛り上がりたい
指導員がワクワクすることがあれば、子どもたちもワクワクします。



どんなあそびでもOK
ワクワクや楽しみは伝染します。
まずは自分がおもしろいと思うことから始めて、そのワクワクを広げていくと、いつの間にか、子どもたちのやる気が満々になっているかもしれません。
それで十分に立派な「指導ができている」と考えられます。
指導員がワクワクした数だけ、指導員の指導力は培われていきます。
ポイントはそこにありました。
これが学童保育指導員の素敵な指導法のひとつでした。



指導員って素敵♪
まとめ


①環境を整える…
②仲間となる…
③あそびをリードする…
④見守るかかわり…
⑤あそびの「指導」…
以上が新人指導員が子どもとあそぶポイント5選でした。
あそびには三間(三つの間)が必要です。





それに加え、指導員の「手間」も欠かせません。



よんま(時間・空間・仲間・手間)
指導員はただそこにいて、一緒にあそぶだけの大人ではありません。
あそびが「あそび」になるには、指導員の「手間」が必須です。



全力であそびにこだわる指導員の「手間」=志
今回はそんな志が高いナイスな指導員になるためのヒントが詰まった内容をお伝えしてきました。
「あそび」を重んじる指導員は最強です。
そして、あそびの楽しさや価値は、あそばないと知ることはできません。
まずは子どもと、どんなことからでもいいので、あそんでみます。
そしてあとから振り返り、ポイント①〜⑤に照らし合わせてみます。
少しずつで大丈夫です。
子どもが日々成長しているように指導員も成長します。
学童保育は、子どもと共に育つ、共育の場です。
すべては「あそぶこと」からスタートします。



よーい、ドン
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。



じゃーねー



